



: 問題2.4.1
: 導体
: 導体
目次
電気の流れ易さを基準に物質を「絶縁体」(抵抗率が
 m以上)、「導体」(
m以上)、「導体」(
 m以下)、
そしてその中間の「半導体」に分ける
ことができる。典型的な導体である銅の電気抵抗は室温で
m以下)、
そしてその中間の「半導体」に分ける
ことができる。典型的な導体である銅の電気抵抗は室温で
 mである。特に金属中には殆ど
自由に動くことのできる「伝導電子」が存在し電気を運ぶ。
抵抗率については後述。
mである。特に金属中には殆ど
自由に動くことのできる「伝導電子」が存在し電気を運ぶ。
抵抗率については後述。
導体(ここでは、金属を考える)を電場中に置くと伝導電子が
動き、片側の表面が正に、他の側が負に帯電する。このような
現象を「静電誘導」と言う。静電誘導の結果、導体内の電場は
ゼロになる。すなわち、導体表面は等電位面になる。よって、
導体のすぐ外側の電場は導体表面に垂直である。
導体表面においてガウスの法則を適用することによって、
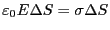 |
|
|
(2.43) |
となる。よって、表面電荷密度 と導体のすぐ外側の電場
の間の関係
と導体のすぐ外側の電場
の間の関係
 |
|
|
(2.44) |
が分る。ただし、 は表面に垂直な単位ベクトルである。
は表面に垂直な単位ベクトルである。
Administrator
平成25年7月6日